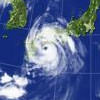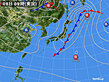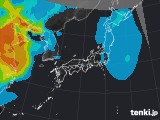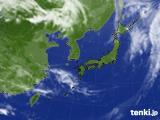ケイトウを題材にした文学作品でもっとも有名な正岡子規最晩年の一句に下記があります。
鶏頭の 十四五本も ありぬべし
この句をめぐり、文学界・子規門下をまきこんで勃発した近代俳句史でもっとも有名な論争「鶏頭論争」(論争自体については、当コラムでもかつて詳しく触れた
こちらの記事をご参照ください)で、死の迫る子規の心に「命」のシンボルのように焼きついた「鶏頭」も、おそらくトサカゲイトウでしょう。
近代から昭和の時代にかけて、ケイトウは時に畏怖を感じさせるほど花襞を肥大化させ、情念や魂が実体化したかのような異様な姿に変化したのです。素朴な庭草から野辺や路地に佇む「異形のもの」へ。そして現代は再び軽やかでかわいらしい姿へと変化しています。それは恐ろしいはずの「妖怪」が、かわいいマスコットキャラクター化してしまっている現代らしい傾向と言えるかもしれません。
けれども、今も昔も変わらない、日本におけるケイトウの普遍的なイメージは、松尾芭蕉の発句に表されています。
鶏頭や 雁の来るとき 尚あかし
この句はハゲイトウの別名「雁来紅」を下敷きにしています。冬が近づく頃やってくる雁。色あせていく初冬の景色の中でなお紅く燃えているケイトウ。
ケイトウはもともと熱帯系の植物で、真夏の頃から花が見られはするのですが、日本の風土の中にあっては、秋の田園風景に溶け込み、晩秋までひっそりと咲き続ける姿が思い浮かびます。そして深まっていく秋を見つめ、沈思しているかのようにやや傾(かし)いで立ち尽くす姿は、やはり存在感たっぷりの大きなトサカゲイトウがふさわしいように思います。
参考・参照
西條八十詩集 西條八十 笹原常与編 白鳳社
人気の草花103種 浅山英一 主婦の友社